日記
|
さてさて、花梨ちゃんの続々編である。
「花梨のオコゲジャム」を「花梨のジャム:カラメル入り」と言い、どうしても少し残ってしまう黒いツブツブを「それってホンモノの証なのさっ」と呆れるほどの立ち直りの早さ。さらには「もっと余計な事」まで。。。 っというか、 ホンネは、(1)後がないっ。(2)カミさんから冷たい視線攻撃を受ける。(3)花梨ちゃんと花梨ちゃんを育てた知人に申し訳ない。(4)産業廃棄物化したらどうしよう・・・なのである。 特に、上記(2)の先制攻撃を受けても、私には迎撃ミサイルは未だ配備されないし、もし仮に迎撃出来たとしても、次には巡航ミサイルの波状攻撃が待っている。また、資金が潤沢であればODAを装えるがその余裕も無いし、これにはどうしても手間隙のかかる外交しかない!っという切羽詰った状況なのだ。 しかしながら、「あっジャムを少しコガしちゃった;」というたった数秒の刹那ではあるが、脳というものは一瞬にしてネガもポジも並列処理してしまうものだ・・・などど、悠長に感心もしている。 またまた話は逸れた;;; 以前おシゴトで取り扱った事があるフランスの某有名食品ブランドのジャムの中に、「ポートワイン入り」とか「ブランデー入り」とかというものがあって、国内上場企業のジャムとは一味違ったのを思い出した。 背後の棚を振り返ると、そこにはお馴染みの「日本酒」や「みりん」に加えて「紹興酒」「サンデマン・ドライシェリー」「グランマニエ」「コアントロ」「カルア・コーヒーリキュール」「マイヤーズ・ラム」「クレーム・ド・カシス」「同・フランボワーズ」はじめ、他各種ワイン計10数本など、カミさんが管理しているお酒がある。ちなみに、特にスイーツ作り系はカミさんの領分で、私はせいぜい<味見させて頂いて貰ってるという程度のレベルのブンザイ>なんですぅ。はい。 さて、この「花梨のオコゲジャム?」って、けっこうフルーツケーキチックだし、甘く熟れたフルーティーな味わいに僅かビター感が・・・っという事であれば、そして、これから初冬・厳冬期と進む事でもあるし・・・。 よしッ! 「オトナのジャムって事でお酒も入れて熟成感を演出してみよう!」などと、アトサキも考えずに発想が飛ぶ。 ところで、どのお酒を入れよっかぁ???? でもご安心あれ。こんなピンチの場合、本体(今回は「花梨のオコゲジャム」)に含まれている良い香りや味の成分と、共通する似た様な香りや味のするお酒を選ぶと、とりあえずは平和にシノゲル。 「今回は、<紹興酒>、<ドライシェリー>、<ラム酒>、もしくは<暑い地域のガッシリした白ワイン>だなぁ。」 ふむふむ・・・「紹興酒は、熟成香が過ぎるなぁ。」、「適当な白ワインは手持ち無いしぃ。」、「ラム酒は味・香り共に締まり過ぎるし。」、「よしッ!ドライシェリーだっ!」(おいおい、今度はキッチンドリンカーに変身ですか?) っという事で、性懲りもせず「花梨のオコゲジャム」ならぬ「花梨のジャム:カラメル入り」に、今度はドライシェリーを加えてみる事にした。 名付けて、《花梨のジャム:シェリー&カラメル入り》 という事になるが・・・さてさて。 やはり懲りもせず、明日もしくは後日へと続く・・・。 |
|
さて、花梨ちゃんの続編である。
山形打刃物のぺティーナイフから竹割り鉈に持ち変えて作業効率は3倍ほどに跳ね上がり、10数個の花梨全部をザク切りしながら塩水に放り込んで、とりあえずの下処理は終了した。 次はいよいよ加熱してのジャム作りに取りかかる。 業務用などの大きなナベだと一気に出来るのかも知れないし、それも打ち出した銅ナベなどがベストだろうか??? でも一般家庭のキッチンではなぁ・・・などとまたまた雑念が。。。 ともあれ、まずは大き目のナベと上白糖、それに味を引き締めるためのレモン1個、攪拌用に木ヘラを用意する。そして、塩水に浸してあるザク切りした花梨の5分の1程度を水気を切りながらナベに移し、いよいよ火をかける。 熱が入るにしたがって花梨から水分がしみ出し、蒸気が上がり始める。 その頃合を見計らって砂糖を少し投入し、木ベラで軽く混ぜ合わせてみる。 すると、なべ底では水分と砂糖が混ざり合ってシロップとなり、ザグ切り花梨に振りかかっている砂糖が未だ白く残っている濃いところの繊維分から少しトロトロと融けはじめ、「照り」というか「ツヤ」というか、が出始める。 あ、これが「ジャム化」し始めるという状態なんだなぁ、などと一人合点つつ、準備していたレモンの1/4を搾る。 その後は、残りの花梨を少しづつ塩水からナベに移しつつ、その都度、砂糖を足しては木ベらで攪拌し、レモンを搾ったり、ジャム化の状態を見るという作業を繰り返して、あとは、美味しい「ほぼ無農薬で無添加の花梨ジャム!」が待っている。 ・・・ハズだった。 かくして、その平穏を破ったのは、私の一瞬の油断だった。 ちなみに、その後を公式化すると<試行錯誤×トライアンドエラー×臨機応変×時間=???>の世界に陥る事となる。(ふぅ;) 火加減のせいか? 攪拌不足なのか? はたまたその両方だったのか??? なんと、ナベ底が一瞬のうちに黒くなり始めた。(要は、コゲた!) 思わず火を止めておナベの中を覗いても、もう元へは戻れない。ここまで頑張ってきたのに・・・と、いくら悔やんでも仕方がない。。。 ・・・あれっ? でもこの匂いって、少し香ばしい・・・??? 花梨のフルーティーな香りと若干の香ばしさが、なんだかちょっと焼き菓子のフルーツケーキチックで、悪くはないんじゃないかなぁ・・・と。。。ナベ底の黒いおコゲって、あ、そうか!「カラメル」じゃないかぁ!(厳密にはちょっと違うが;) そこで、ちょっとなめてみる。 花梨の甘く熟れたフルーティーな味わいに、アルかナキか程の僅かなビター感が加わって、けっこう美味しい。 スイーツ作りが好きな人はご存知かと思うが、砂糖に水を加え加熱して適度に焦がせばカラメルが出来る。それに水あめや生クリームを加えたりすればハヤリの「キャラメル」になる訳である。 確かに・・・「花梨のオコゲジャム」ではちょっとカッコ悪いけど、「花梨のジャム:カラメル入り」と言えば、なんだかフランス有名食品ブランドのジャムみたいで、カッコ良いかも☆☆☆!(なんとも呆れた話だ;) こうなると、若干は残ってしまう黒いツブツブも「バニラビーンズを使ったアイスクリームにだってツブツブが残ってるし、それってホンモノの証なのさ。」っという具合にあっという間に立ち直り、さらには「もっと余計な事」まで試したくなる。(ヤメとけば良いのに;) 明日に続く・・・。 |
|
こんばんわ。Aoyamaです。
さて、花梨は、芳香用として車の中に入れるという使い方もあるが、 香りのピークを過ぎてしまうと、なんだか可愛そうでもある。 喉に良いとかで、焼酎やホワイトブランデーに漬け込んで「花梨酒」を作るという事もある。 おそらく、これが一番メジャーな使い方なのかも知れない。 また果物なので「ジャム」という手もある。 先日、知り合いの方から「花梨」を10数個いただいたので、 全部ジャムにしようと決心。 実際に花梨の皮を剥いた事がある方ならお分かり頂けるかと思うが、 ご存知の様に、花梨の実は非常にデコボコしている。 さらに、皮が非常に堅く、加えて皮の下の実も堅くザラザラとした堅い木質も混ざる。 芯の部分に至ってはほとんど木質と言える。 最初の2個までは、愛用のよく研いだぺティーナイフ(もちろん山形打刃物)を使っていただが、薄く精度の高い刃ほどみるみる切れなくなっていく。 切れなくなったら研げば良いのだろうが、その分だけ時間がかかる。 手間隙を惜しまないにしても、剥いた花梨の実は、放置すれば酸化してどんどん茶色になってしまう。 だから、りんごの実と同様に切断面を塩水処理しなければならない。 それに、元々がとても切れる山形打刃物なので、万一焦って手が滑ってしまったら・・・などと脳裏に雑念が走る;。 これじゃダメだっという事で、急遽「竹割り鉈」を取り出す。 「竹割り鉈」は小型の鉈で、もちろん本来は竹を割るための刃物だが、花を活ける時にも花木の余計な枝などを払うのにも便利なので活花愛好家にも重宝されている。 しかし今回は、それを花梨の皮向きと芯抜き、そして実の切り分けに使ってしまったが、なんと、これが正解だった。 バシッツ、ザクッツ、グリッツ、サク・サク・サク。。。 作業効率は3倍ほどに跳ね上がった。 ・・・・・・・・明日に続く。。。 |
All Rights Reserved by shidareo
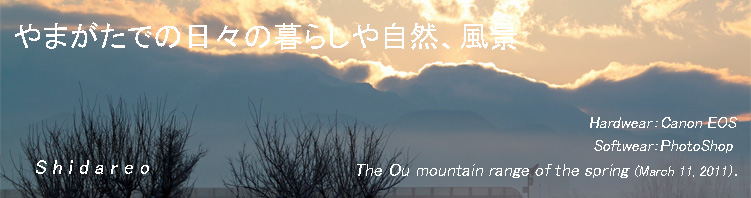








・・・っという事で、性懲りもせず「花梨のオコゲジャム」ならぬ「花梨のジャム:カラメル入り」に、今度はドライシェリーを加えてみる事にした。
名付けて、《花梨のジャム:シェリー&カラメル入り》 という事になるが・・・さてさて。
ところで、シェリー酒はどの位入れれば良いんだろう???
そんなの、入れてみなければ分らない。
だって、工場の様に、最初から果実の糖度と重量を測り、上白糖の量を設定してスタートした訳じゃなく、ただ単に、特別に添加物を加えたりしない範囲で、果実に砂糖と温度を加えて行けば、それなりに一定の糖度に達した時に自然にジャム化する、という事を前提にした、言わば、成り行き(行き当たりバッタリ;)にまかせた様な事をやっていたのだから。
でも、こんなの料理(料理:重たく言えば「理を計る」という意味だそうだ。)って言えるんだろうか?
・・・今さら○理屈をこねても仕方ない。それよりさっさとジャムをこねろ!である。
そんなこんなで、
ほとんどジャム化した花梨に少しづつシェリー酒を加えては攪拌しそして味見をする。
これを数回は繰り返すこととなった。
ん、こんな感じで良いだろう!
ほぼ無農薬(?)そして無添加でのホームメード「花梨ジャム」を簡単に作るつもりが、「花梨のオコゲジャム」となり、「花梨のジャム:カラメル入り」、そして「花梨のジャム:シェリー&カラメル入り」という波乱万丈な変遷を経ては来たが、あとは余分なアルコールを飛ばす程度に2〜3分加熱し、火を止めた。
その香りに誘われてか?カミさんが声をかけて来た。
「あ、作ったの?」
(カミさんがおもむろにナベを覗く。)
「ふふふっ、コガしたな。」
(バレるのは仕方ない。笑顔でとりつくろい、これまでの経過を説明する私・・・。)
「けっこう美味しいじゃない。」
(したり顔の私!)
「ジャムは、最後にメッシュで裏漉ししなきゃね。それがたいへんなのよ。」
(え、そんな事しなきゃならないんだぁ?食べれるのに。)
「まだ細かいカケラが残っているでしょ。でも花梨は仕方ないのよ。」
(そうかぁ、やはり繊維分が頑丈なんだぁ・・・。)
「じゃぁ、裏漉しはしてあげるから。」
(このひとことで主導権が移ってしまったけど、ま、有り難い!)
今度は軽く再加熱して流動性を高め、冷めないうちにメッシュに移しては、木べらで裏漉しを始める。こうなると、私は脇で見学しつつ誉めるしかない。(これも外交上必要なのだ。)
それにしても、なかなか手際が良いものだと、しばし感心する。
「なめてごらんよ。」
勧められるままに裏漉ししたばかりのジャムをスプーンですくってなめてみると、あれっ?
味が一段とまろやかになり、そして均質になっている!
よっしゃ! ほぼ無農薬・無添加《花梨のジャム:シェリー&カラメル入り》の完成!である。
今回は、幸いにもカミさんのミサイル攻撃も受けず平和裏に進んだ事に関して、心の中(だけ!?)で深く感謝しつつ、再び再加熱し、小分けして瓶詰めにしたのは言うまでもない。 <END>
<追伸1:花梨ジャムの楽しみ方(スタンダード編)>
パンの香ばしさと、熟した果実感との相性がとても良いので、なんと言ってもフランスパンやドイツパンに有塩バター(発酵バター大歓迎!)を薄くぬり、好みの量のジャムをのっけていただくのが一番!。もちろんプレーンヨーグルトやアイスクリームにも。
<追伸2>
以上は、ほんの出来心で花梨のジャム作りを楽しんでみたという経過です。
しかしながら、花梨のジャムは意外に美味しいオトナの味ですし、特に果物が豊富な当地山形では原料調達もさほど難しくないかと思われますので、プロ・アマ問わず、ぜひ一度お試しあれ!