日記
|
>先入観ってただの幻想なんで・・・(中略)・・・ともかくも、それ以降、カミさんの手作り焼き菓子系レパートリーに「干し柿入り」が加わった。
っという具合に、<柿>はフランス料理系デザートにもOKだし、<干し柿>は洋風焼き菓子にもOKだというのは分った。でも、ただ単に干し柿をほおばる以外に(それはそれで美味しいのだが)、なんというか・・・日本的な楽しみ方はないのだろうか??? 和菓子の世界でも多様な使い方をされているが、私が一番好きなのは、<柚子しろ柿>という京都大徳寺のお菓子。柚子のピール(砂糖煮)を干し柿で海苔巻きみたいに直径3cm位に細長く包んだもの。で、食べる時は厚さ3mm程度に薄く輪切りにしていただく。 TVの特集番組か何かで、金沢のお婆ちゃんの手作りシーンが紹介されていたのを見て、先ずはトライしてみようという事になった。しかし、家庭でも比較的簡単に作ることが出来るが、実は、作ってから食べ始めるまでに<根気>がいる。 なんと!柚子と干し柿の味わいがバランス良く馴染むまでの1〜2年を冷凍庫で寝かすのだ。(けっこう糖度が高いので、凍らないしほとんど硬くならない。) もしも、喰い気が勝り、根気負けして早く食べてしまうと、ただ単に柚子と干し柿を同時に口の中に放り込んで喰った!というだけで、あの絶妙なハーモニーが味わえない。 だから、ひたすら待つ。 これまた良い感じにスローな世界で、茶人などには非常に好まれると思う。さらには、キリリと冷しや硬質辛口の大吟醸酒などと合わせてもかなりGoodだった。 今後トライしてみたい事は「干し柿を甘味料として料理に使う」事だ。 なんでも、そのむかーしの山形は、砂糖は高価すぎて庶民は使えなかったし、ビート(砂糖大根)も無かったので、料理の甘味料として「干し柿」が使われたそうだ。そこで、特に郷土料理系の煮物の隠し味などに「干し柿」を使ってみようと思っている。 ま、好みや慣れ、それに先入観や素材同士の相性の問題などもあるだろうが、おそらくは、干し柿の持っている特性(意外に癖の無い甘さ、繊維分の粘っこさ、熟した果実味がもたらす熟成感など)が、単に砂糖を使うよりも、味に奥行きというか立体感が出て来るものと非常に期待している次第である。 その後の結果は、追々レポートしてみたいと思っているが、興味のある方もぜひトライしてみてはいかがでしょうか。 ■追伸:焼き菓子系の場合、干し柿を予めお酒(ブランデーや各種リキュール等)に漬け込む事は、現状は控えている。何種かトライしてみたが、もともとの干し柿の味や香りが淡いので、どうしてもお酒の味や香りの方が勝ってしまうのだ。もしかすると10〜20年という長期に渡って漬け込むと上手く馴染むのかも知れないけど、今の段階ではそれは後世にお任せする事にしておく。 |
|
> 子供の頃は、干し柿の色が黒っぽいのと、姿がちょっとミイラチックだし、フレッシュで冴えた味わいでもないので、食べなかった
>・・・というよりも、キライだった。・・・(中略)・・・干し柿の事もなかなか面白いので、後日もう少し書き足してみようと思う。 さて、私たちは、ふたりの方から干し柿の再認識のキッカケをもらった。 ひとり目は、20年程前に私の家にホームステイしたフランスの青年だ。彼は、パリ大学に在学しつつ早稲田大学に何年か来ていたが、縁あって、私の家に数日間ショートステイする事となった。 あ、何故にホームステイなんてメンドクサイ事を受け入れたかというと・・・、子供には、日本人ではない人とも出来るだけ臆することなく接する事が出来る様になって欲しいなと願っていたのだが、それには留学させてしまうのが一番。でも・・・正直「ナイソデハフレナイ」だ。それに、未だ小学生だったし〜。 だったら、いっそ来てもらえりゃ良い。年に1〜2回のショートステイ受け入れというレベルなら、経済的負担もたいした事ないし、家族の負担も限度内だし、珍しいお客様ってのも楽しいし・・・っという感じで、思い切って、且つ気軽に始めた。 そんなこんなで、秋にステイした彼に、季節の果物である「柿」を出してはみたが、さてさて、柿という果物を説明するのに詰った。 そしたら、フランスでも柿は<Kaki>だという。 柿という食べ物としてのフルーツは、日本から木を移植して広まったので、そのまま<Kaki>と言ってるよ、と話してくれた。 フランス語の<柿=Persimmon>は、おそらくは、原種に近い様な、日本古来の塗料である「柿渋」を採る様な、硬くて小粒で渋すぎて食べれない様な、あんな柿を指すんだろうか??? ともあれ、味覚を表す言葉の数が世界一多いと言われるフランスでも、食べ物としての柿は日本語発音の<Kaki>でも通るらしい。 ふたり目は、山形の工業系某企業の社長さんの奥さま。 なんでも、頂き物の中に「干し柿」があったらしく、さてどうしようかぁ〜となったらしい。そこで「焼き菓子のフルーツケーキにはドライフルーツが入ってる」の応用バージョンを思いついたらしく、時々「干し柿を入れたパウンドケーキ」を焼くんだよとの事で、何かの折にそのケーキを頂戴した。 秋になると、毎年毎年「今年も干し柿づくりが始りましたぁ。」という報道が流れるし、ごくごく日常的な風景としての「柿簾」を見たりしてるし、さらには、幼い頃のイメージなど先入観があったせいなのか(?)、先ずは「え〜ッ、干し柿ぃ〜?!」っという感じで受け取ったが、心がこもったせっかくの手作りケーキを食べてみると、素直に「あっ、美味しい!」であった。 考えてみると、先入観ってただの幻想なんで、それが改まるなんて、こんな些細なキッカケでOKなのかも知れない。いやいや、前頭葉が支配する表層的な言葉や理屈での理解ではなく、味覚という深層部分も加わっての納得だからなのだろうか? ともかくも、それ以降、カミさんの手作り焼き菓子系レパートリーに「干し柿入り」が加わった。 ・・・後日に(ちょっとだけ)続く。。。 |
>記事内容についてはおそらく後日紹介させいただけるかと思っていますが・・・・・・・・・
>2009.11.27:shidareo: 身近な湧水という事で、白鷹山北裾の湧水「五番御神酒(ゴバンミキ)」の紹介が、昨日の読売新聞に載っておりました。 ま、地理上(地球儀レベル)の妙と言えるのかも知れませんが、 日本、特に日本海側の中北部の水は、かなり良いと思っています。 その中で、やまがたに住み日々暮らしている私たちは、海水から真水をとるプラント、 しかも・・・それを飲んで美味しいと言えるまでにしちゃってくれる「壮大な自然のプラントの中に住んでいる」んですよね。 それで田畑を潤したり、地酒をつくったり、コンクリートを練ったり、洗濯や洗車までしてる。 水道料金は欠かさず払わせていただいておりますが、そうゆー話じゃぁなくって(汗;) ・・・わかっちゃいるけど、私だって、そのお返しを未だなーんもしちゃいない。。。。 |
シャキシャキ:みずな(日の出06:39の4分前)
気温がやや高めで、早朝は曇り。日の出前から少し風が巻いている。 散歩に出て間もなくは、蔵王山系の竜山や雁戸山もよく見えていたが、 あっという間に宮城県の方からの厚めの雲の覆われてしまい、 市街地と西蔵王程度までしか見えなくなってしまった。 この時期は、木々達も冬支度を終えて眠りにつくし、冬枯れ寸前。 若い頃よりは平気になってしまい「ま、毎年こんなモンだろう」としているが、 冷たい雨や霧、ミゾレなんかが降れば、やはりちと寂しい。 そんななか、大きくは育っているが柔らかさとハリを兼ね備えた、 初初しいシャキシャキの「みずな」を畑で見つけた。 これも、この季節の光線量の少なさや、高めの湿度と低めの温度の ナイスバランスがもたらしてくれるものなんだろうな。 |
All Rights Reserved by shidareo
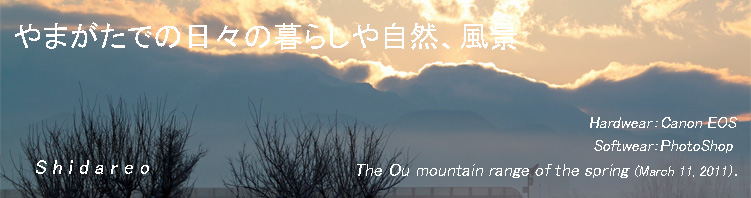










もう12月中旬という寒い時期にも係わらず、アスファルトとコンクリートの隙間から成長して、ちゃんと花をつけている。
一般には雑草のタグイとみなされているが、その茎の伸び方や、花の配置やその大小、開き具合の分散度といったパターンというかコンポジションは、さすがにキク科の植物そのものだ。
ま、ヒメジョオンは明治時代、ハルジオンは大正時代に帰化した雑草と言われてるんで直接参考にされた訳ではないだろうが、和服や日本画などに施されている花などは、こんな作為性のない自然なパターンを写し取ったものなんだろうな。