日記
犬っ子散歩コース脇のヤナギに、綿毛(種)が付きはじめた。
種が熟すと、丁度タンポポの種の様に風に乗って空中を浮遊する。 このヤナギの綿毛が大量に浮遊する時期がある。 その日和というのは、湿度の少ない薄曇〜晴れの日で、 風は微風、気温は18℃前後。 そんな日は、人にとっても気持ちの良い。 この綿毛であるが、イワナやヤマメにとっては、 どうも、水生昆虫である小さなカゲロウと間違えるらしい。 ヤナギから離れた綿毛は、粉雪というよりも、 大き目のダイヤモンドダストの様にキラキラと浮遊し、 心地良い初夏の微風に乗って周囲の林を抜けたり、 あるいは川面に降りたりもする。 その川のイワナやヤマメ達は、 いつも捕食している小さなカゲロウなのか、 それともヤナギの綿毛なのか、混乱をする。 そんな日は、難しいと言われるフライフィッシングでも 沢山のイワナやヤマメと出会える。 昨日、所用というか・・・東北6県の会員で組織されている 東北フィールド射撃協会という団体の会議があって、 今年度から監事のお役という事で、宮城県の鳴子まで行って来た。 鳴子は、オオカミと犬との交配種を題材にした 熊谷達也の小説「ウエインカムの牙」の舞台にもなっているので、 興味はそれなりにある…が、昨日に限っては、 鳴子の手前の「山形県最上町」の方に気持ちが向いている。 実は、最上町には、今年で27年目にもなるが、 毎年キャンプと釣りを楽しんでいるフィールドがある。 息子が3歳になった頃からずっーと、先代の犬っ子も、 今の犬っ子も、カミさんも、家族みーんなで楽しんでいる。 フライフィッシング全般を学び、山菜を学び、 部落の猟師からはクマ肉をごちそうになり、 地元のフライフィッシャーと腕を競ったり 川の生態を学んだり、プロのロッドビルダーや、 彼の大場満郎さんとも会えたり、 時には、周囲360℃全て「ホタル」に巻かれたり、 鉄砲水に近い怒号の様な川の姿に恐れたり…と、 もしかすると、私達家族の山野遊び全般のベーシックというか、 教科書というか、師匠の様なフィールドである。 だから、 今年の渓はどうだろうか?とソワソワしていたのだが、 残念ながら、昨日は寄って来れる時間も雰囲気も無かった。。。 車窓から遠望した限りでは…だが、 今頃の時期としてはけっこう残雪が多めで、 その場所(見える尾根や谷のカタチ)も、 例年とは少し異なる様だった。 |
今朝も寒めだ。
近くの田には、まだ水が入っていない。やはり遅れている様だ。 昨日は、近くの高い山々に雪が降ったし、(ぱっと見で、標高1.500m以上かな?) 後世に伝えるべきオモムキのある年になりそうな。。。 ところで、曇り空とか雨の日には、緑色が綺麗に見える。 日光の眩しさに幻惑されないからだろう。 「ニセアカシア」の若葉も透明感あふれる。 ところで、荒地にも平気で生えるこのトゲトゲしい 「ニセアカシア」だが、花の香りが、なかなか良い。 香りが広がるという横軸もあるが、 鼻腔から脳みそを垂直に抜け、頭のてっぺんにある髪の毛の一本を 軽くツンと引っ張ばりつつ、空に帰る…という感じの、 心地良い縦軸の刺激も含まれるので、いつも楽しみにしている。 (その香りを詰め込んだリキュールづくりなんかも面白いかも。) その「ニセアカシア」の花だが、これも喰える。。。 「藤の花」と同様に、天婦羅が良いらしいのだが、 私は、軽く湯掻いて冷水で冷してサラダに添えようかと思っている。 花を食べる習慣は、実は、世界でも珍しく、日本国内でも限られる。 <花食文化>を研究している学者もいるくらいなのだが、 その「特異文化」のまっ只中で日々暮らしてる「やまがたの我々」とっては、 とりあえず「関係な〜い」話である…のかなぁ???。 ・・・・ま、いいかぁ〜。 |
今朝早くに、「ドン・ドン・ドン」っと花火があがった。
5/13(木)という、カレンダー的にはかなり中途半端な日なので、 地域のお祭りとか学校の運動会でもなかろうに。。。 あ、そういえば、この辺の田に水が入るのが遅れていたが、 犬っ子散歩途中に「今日あたり入るらしいよ」という話を 農家のオジサンから聞いたのを思い出し、 きっとその合図だろうと、勝手に納得した。 ご近所の庭にある「フジ」の花が咲き始めた。 「フジ」の花って、京都の舞妓さんのカンザシを思い浮べてしまって、 この自分の単純さに、一瞬情けなくなる。(ま、素直で良いのだが;) 「フジ」の花…山の「フジ」の花が咲く頃は、 たくさんの昆虫達が活発に活動する。 だから、その昆虫達を捕食するヤマメやイワナの行動に 大きな変化が出てくる。 その変化とは、水中を流れてくる虫やミミズよりも 水面を流れてくる虫や、水面すれすれを飛ぶ虫に対して より興味を示すようになるのだ。 虫を模した毛鉤釣りにも、水中勝負と水面勝負とがあり、 水中勝負の方ならば生きた餌で釣る事ももちろん出来るが、 この時期辺りから、毛鉤釣り独特の水面勝負である 「ドライフライフィッシング」が佳境に入る。 どんな感じかとザックリ言えば、 魚が水面を割ってニュッと顔を出したり、パシャっと跳ねたりしながら 虫を食べているので、先ずはその姿を目で確認する。 次に、食べてる虫に似せた毛鉤を、 その魚の1m〜1.5m上流にそっと置き、ごく自然に流す。 そうすると、虫と間違えて喰いついてくれる…「ハズ」である。 ま、言えば簡単だが、そうは問屋は卸さない。。。 所用が重なったりして、釣行までなかなか至らないが、 片思いの恋人の様に、想いが募れば募るほど、夢と楽しさは、増す。 あ〜、 一週間くらいテント張って、犬っ子達連れて、釣りとキャンプしないなぁ〜。 |
「田に水が入る頃になると寒くなる。」と聞かされるが、全くその通りだ。
昨晩からの雨は、今朝にはあがったが、ちょっと寒く感じる。 でもこの度の雨は、山野や畑の緑を大きく育て、 ヤマメやイワナに新たな酸素と餌を与える事だろう。 西洋花梨(マルメロ)の花が咲いていた。 良く見ると、その蕾はまるで「いちごソフトクリーム」だ。 花びらが薄めでとても柔らかく、開き始めるとすぐに、 弱い風などでも、ヒラヒラというか、ヘナヘナになってしまい、 意外にカタチが崩れやすい。 ところで花梨系の「ジャム」や「ジュレ」が大好きで、 麦の焼けた香ばしさ(特に自然酵母系のパン)に合う。 飲物は、ま、コーヒーやお茶も良いけど、シャルドネ系や ピノ・ブランなどのスッキリ系辛口白ワインがあると嬉しい。 それもスパークリングやシャンパンならもっと嬉しい…v(^^; (また喰いモンに走ってしまったので、話題を少しだけ変えよう。) 花梨の瘤(コブ)とか根っこの太い部分は、とても良い材料になる。 木目が複雑に入り組んでいて、磨くと浮き出る。 主に、高級クラフト系の材料(例えば、カスタムナイフの柄の部分や、 釣竿のリール取付部分など)として使われる。 でも、製材や加工に手間隙がかかるし、技術もいる。 クラフト好きな私も、以前に、釣竿のリール取付部分として 半加工された部品を購入し、あとは自分で微調整と仕上げをして 使った事はあるが、確かに良い物が出来るものだ。 ...もっと詳しく |
朝の犬っ子達との散歩も、いよいよ緑に包まれて、
「青嵐(アオアラシ)」の季節も間もなく佳境入りつつある。 道すがら、太く古いブドウの木から生えた若葉が 少し大きくなっているのに気が付いた。 写真を撮っていると、 「他の木は切ってしまったけど、これは切らなくて良かった〜」と、 畑の持ち主が話しかけて来てた。 ナイヤガラで、出荷用ではなく今では自家消費用だそうだ。 そんな話をしていたら、 別の散歩中のオジサン(農家OB)もわざわざ足を止めて、 「ぶどう、もう出てるべー」と。 どうやら、この中心の「ぶどうの赤ちゃん」の事の様だ。 さらに続けて、 「この二つのうち、片方をトル(間引く)と、良いブドウになるんだぁー。」 と、丁寧にアドバイスまで頂戴してしまった。 ま、今日の私の頭の中では、 「ぶどうの葉っぱなんかも美味いだろうな…。」 「イタ飯だったか?トルコ飯なんかで使ってたけど、どんな料理だっけ???。」 「間引いたぶどうの若葉と赤ちゃんは、ピクルスが美味しいかも???…♪。」 なーんて事が渦巻いていたのだが。。。(><; …道端のペパーミントも勢力を拡大し始めて、すでに初夏の兆しでもある。 たまにゃ「ミント水」も良いしぃ〜♪ 「桃のシャーベット」に、ミントを添えてぇ〜っと♪ (↑↑↑↑ いつまでもやってろ! 死ぬまでやってろ!) |
昨日の日曜は、山菜の「ホンナ」を採りに谷筋をトラバース。
周囲は、黒木(針葉樹)や雑木(落葉広葉樹)に囲まれていて、夏でも涼しい。 ちょっと上にはまだまだ残雪があって、冷たい雪解け水も混じる。 <ヤン・ワッカ・タイ>という語がある。 アイヌ語で、<冷涼な・川の流れる・森林地帯>という意だそうで、 「やまがた」の語源説のひとつとも言われている。 やや広域な場所を指す言葉なので、この場合の「川」というのは、 「最上川」の事なんだろうと推測しているが、 こんな枝沢だって、末は最上川となるので、 ここは、<ヤン・ワッカ・タイ>の超ミニ版というか、 小宇宙という事にしておこう。 ところで、こんな谷筋のやや緩めの斜面の一部に 腐葉土が作られ続けてる様な場所があるが、 そんなところに「ホンナ」がある。 さて、帰り駄賃にと、峰に張り付き「コシアブラ」を採りつつ登り詰め、 さらに隣の峰に渡って、その稜線に沿ってまっすぐに下る。 下山途中、人間のそれよりも大きな排泄物を4箇所で確認。 とりあえずは「出くわしません様に」と、 時々「カシワデ」をパンパンと打ちながら、無事下山。 「気を付けよう! 道迷いと、黒く大きな野生動物との遭遇」(もろに字余り;) |
All Rights Reserved by shidareo
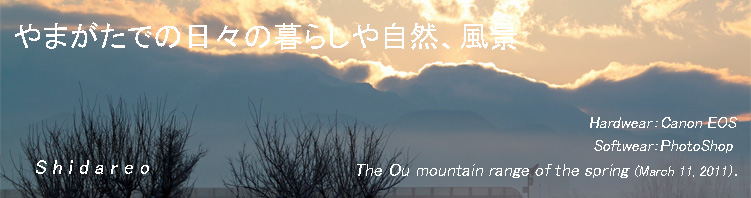












水が入った田もあり、蔵王山系の端っこの山裾が
かなり鮮明に映りだしていた。
(↓↓↓ タネ明かし。)
こんな日は、大鳥池はじめ、各所の山の沼湖にも
その周囲の景色が映り込んで、さぞかし綺麗だろうなぁ〜。
畑で栽培されている、イワユル「作りウド」も大きく葉を広げていた。
ま、畑で、茎を土で覆いながら管理し育てているので、
茎の白い部分が大きく柔らかく、出荷用には良いのかも知れないが、
山に自生している「通称:山ウド」ならば、「ウドの大木」近い。
「ウドの大木」から、宮沢賢治の言う「デクノボー」を思い浮べる。
漢字で書くと「木偶ノ棒」だろう。
良い木材になる様な木であれば、いずれ人によって切られてしまい
植物としての命は絶たれてしまうが
「デクノボー」みたいな木の方が、命としてはまっとうされる様だ。