∟在来作物/農産物について
車窓に広がる紅葉を目にしながら、
車は山間部から日本海へと向けて移動します。 と、その前に休憩がてら寄り道。 あつみ温泉にある 足湯カフェ『チット・モッシェ』で一休み。 ここは、私も以前から行ってみたかったところのひとつ。 前に一度来たときに残念ながらお休みだったために願い叶わずで、今回初めての来店になります。 のんびりと足湯につかりながら飲み物がいただけるとっても癒し系スポットです。 朝から心配していた雨雲もいつのまにやらどこかへ行ってしまい、 のんびりとした時間を楽しむことができてよかったです。 出発する頃、辺りは暗くなっていました。 足湯で一緒になった見知らぬ人たちと、のんびり会話なんていうのもなかなかいいですね。 右側の写真は、足湯カフェの近くにあったかわいい雑貨屋さんです。 
|
藤沢地区を後に、一向が次に向かったのは
「温海かぶ」を作っている一霞という集落です。 ここは旧温海町にあるのですが 国道345号線を新潟方面へ向かいます。 この国道は、その昔新潟へ続く道として栄えた街道で、 「田川かぶ」「温海かぶ」といった 在来のかぶを焼畑で作る地域が点在しています。 春の時期には菜の花が咲き乱れ、それはそれは綺麗な景色を楽しめるそうです。 残念ながら、春の時期は忙しくなる「山菜屋」という仕事上、 未だに一度も観ることができていないのがとても悲しいです。 かぶの他にも「蕎麦」「栃の実」「しな織」といった文化があり、 五穀豊穣を願って生まれた祭事や農民歌舞伎や能など、 古くからの伝統が今に残っているとても魅力的な地域です。 「鶴岡市観光連盟-温海エリア-」 その他の鶴岡市観光についてはこちらからどうぞ。 →「鶴岡市観光連盟」 さて、話がそれてしまいました。 一霞温海かぶ生産組合の組合長佐々木さんに説明を伺いながらの見学です。 この工場は昭和59年に設立され、佐々木さんは3代目の組合長なのだそうです。  焼畑農法により、無肥料・無農薬で作られた温海かぶは、各組合員のところから工場へ運ばれます。  その後、塩と砂糖、酢だけで漬け込んでいくわけですが、 以前、この甘酢漬けを首都圏に売り込んだ際に あまりに綺麗な色をみて、着色料が入っているのではないかといわれたこともあったそうで、 「酢」だけで色が出るということをわかってもらうのにちょっと大変だった。 といった話もあるくらいとても綺麗な色に仕上がります。 その元となるのがこのきれいなかぶの色なのです。 採りたてのかぶは、表面がきれいなパールのような光沢があります。  できあがったかぶ漬けは、お母さん達の手によって袋詰めされます。  お忙しい中、私たちの見学を受け入れていただきました 一霞温海かぶ生産組合のみなさんありがとうございました。 |
その後、バスに戻り、
「栃の実」のお餅をおやつとして配らせていただきました。 これは、当店山菜屋.comでお世話になっている、 旧朝日村の「とちのみ加工所」のおばあちゃん達に 朝作っていただいたもの。 今回、この「栃の実」について お話することができなかったことが一番の心残りです。 全国的に「栃の実文化」が失われつつある現状の中、 この地域ではおばあちゃん達が中心となって 地域に伝わるこの伝統を上手に活用しています。 その取り組みなどをお伝えしたかったなぁ。と、とっても残念でなりません。 山菜屋.comではこの「栃の実」を応援しています。 興味のある方は是非、見てやってください。 「山菜屋.com-栃の実のページ-」 
|
次に私たちが向かったのは
在来作物「藤沢かぶ」が作られている畑。 畑といっても山の急斜面の木を切り倒し、 その後焼畑をして作られるところで、 これの凄さは、 現場を目の当たりにしないと伝わらないかもしれません。 毎年場所を移動して作られる「藤沢かぶ」ですが、 今年の場所は比較的集落に近いところでした。 それでも、山道は曲がりくねった細い泥道で、 大きなバスが畑まで行くことはちょっと危険と判断し、 少し下にあるお不動さんを祭っているお社のところから 歩いて登ることにしました。 森林浴を楽しみながら山道を15分ほど歩くと 目の前に切り立った急斜面が目に飛び込んできました。  その急斜面は一面緑の葉に覆われ、 ところどころに腰丈ぐらいの切り株が点在しています。 その斜面の急なことと葉っぱがすべて「かぶ」ということに驚きながら 足元に注意して畑の中へ入ります。  江頭先生の「藤沢かぶ」についてのお話を聞きながら、 かぶを引き抜き葉を使い上手に土をふき取り一口「ガブリッ。」とかじってみます。 そのみずみずしさと、おいしさにびっくり! みんなニコニコ顔でほおばっていました。 
|
東京第一ホテルに集合し東京方面から参加の方々と鶴岡駅で合流し、
先ずはじめに向かったのは 「つけもの処 本長」さん ここは、明治の末から「野菜の粕漬」の製造を始めて90余年という 長い歴史のある漬物やさん。 スローフード山形のメンバーでもあり「在来作物を使った漬物」にも 力を入れている地元でも老舗の漬物やさんです。 漬物が作られる工程を見学できるようになっており、 日々多くの方々が見学に訪れます。 2007年春に店舗を新築しましたが、 新店舗建築の際にも「今までの趣をそのままに残して欲しい」 という声が周囲から聞かれるほど愛され続けているお店です。 ご覧のとおり、みんなの想いを受け、 歴史の趣を今に伝える店構えに生まれ変わりました。 先ずは、お店の歴史や看板にまつわるお話を伺い工場の見学に進んでいきました。 |
レポートが遅くなり、
本当にお恥ずかしいところではありますが、 先に行われました 「庄内在来作物探検&食談会」について報告いたします。 写真は、探検場所のひとつ「温海地区一霞」にある加工直売所で撮った集合写真です。 去る2007年11月10日 スローフード山形の庄内ブロックで企画させていただきました 「庄内在来作物探検&食談会」ですが、 天気予報が芳しくない中、山への探索ということで、 庄内ブロックメンバー一同、空を見上げハラハラしながらの探索でしかが、 雨も降ることなく無事終了できたことに 心から感謝しているところです。 前回行った探索会は、スローフード山形のメンバーの参加のみでしたが、 今回は「スローフード東京」「スローフード杉並」「スローフード宮城」といった 他の地域の仲間にも多く参加していただき とても有意義な1日を過ごすことができました。 遠路はるばる参加いただきましたみなさん、ありがとうございました。 |
先日の「山形スローフード協会」で行われた
『赤カブ街道を巡る&食談会』で写してきた 在来作物「藤沢かぶ」の写真です。 土に埋まっている部分は白く、 出ている部分は紫色になっています。 今は6人でグループを作り、毎年木を切り倒し、 焼畑をして大切に大切に育てているそうです。 連作することが出来ず、毎年種をまく場所を移動しなければならなくて、 木を切り倒すことができる山の斜面を見つけるのが大変なんだそうです。 かぶを収穫した翌年はアズキなどの豆類を植えて、 その後、杉の苗木を植林するのだそうです。 植えた杉の木が大きくなり、それをまた切り倒し焼畑して… というサイクルで脈々と受け継がれるのですが、 今植える杉の木を、今度切り倒すのは50年後という話に みんなため息を付いてしまいました。 守り続けるということは本当に大変なことですね。 ...続きを見る |
今日はスローフード協会のみなさんと
在来作物の「赤カブ」や「日本海の海水から作る塩」の見学を行い、 夕食会と座談会といった食談会が行われます。 ここ何週間、週末になると雨模様でした。 数日前までは天気予報も「週末は雨」といった具合。。。 ちょっぴり心配していましたが一昨日あたりから、なにやらうれしい雲行き。(*^_^*) 夕べはいきなりの土砂降りで、ちょっぴり心配したけれど、 早朝の濃霧から一気に天気は晴れマーク! 今日は朝から「アル・ケッチアーノ」さんへ食材を持って行きシェフの奥田さんとちょっと談話。 チャコ:『今日は、江頭先生方と赤カブの見学会なんです。 雨を心配したけど、晴れてよかったです。』 シェフ:『今日は晴れますよ。』 いつものようににっこりと微笑むシェフ。 シェフ:『今日はうちでも取材が入ってます。取材の時は不思議と晴れるんです。』 自他共に認める晴れ男「奥田シェフ」恐るべし!です。 シェフの晴れ男伝説 私も、奥田シェフほどではありませんが、自称「晴れ女」。 今日一日、有意義に過ごすことが出来ますように。 カメラ持って行きます。 画像は、ここや「山菜屋どっとこむ」「山形スローフード協会」のサイトにてUPしたいと思います。 山菜屋どっとこむ 山形スローフード協会 写真は、昨年の11月22日に訪れた時の赤カブ畑です。 ...続きを見る |
「山形在来作物研究会」入会申し込み用紙です。
「山形在来作物研究会」の入会申し込み用紙を UPしようと思っているうちに日は過ぎて行き・・・ 研究会の公式ブログサイトがオープンしましたので、 ご入会はこちらからどうぞ。(^_^;) ⇒入会してみっがなぁ〜。 |
|
東京都港区芝浦にある、
「キャンパス・イノベーションセンター」(JR山手線田町駅芝浦口すぐ)内 「山形大学農学部・東京サテライト」にて、公開講座が開かれます。 講座の内容は「やまがた発!在来のくだものとやさい」 入場量は無料です。 興味のある方、足を運んでみませんか。 |
「山形在来作物研究会」なるものに入ってます。
山形大学の農学部と一緒に山形に伝わる伝統作物などについて研究したりしてます。 2003年に発足したこの会も現在は会員数330名と年々増えていってます。 2005年の研究会主催行事が 11月19日20日と開催されます。 19日「温海カブの栽培と加工見学会(夕食付)」 20日「公開トークショー2005 食べなきゃ庄内」 パンフレットを掲載しますのでご興味のある方いかがですか。 |
copyright/sansaiya













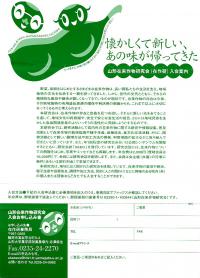


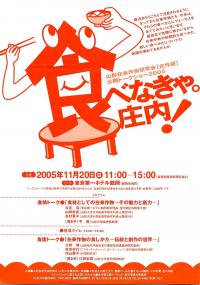



イル・ケッチァーノでの食談会へ突入です!
SF山形の小山会長よりご挨拶を頂き
江頭先生にマイクが渡りました。
バスの中でもず〜っと
畑の説明や在来作物の話をし通しだった江頭先生。
いつもいつもお世話になります。
と、いうことでここでの話はさっと挨拶程度にしてマイクは奥田シェフに。
乾杯の後、シェフからは目の前に並べられているお料理の数々を説明していただきました。
お食事をいただきながら、
各会の代表の方々に今日の感想と地域での活動などを紹介していただきました。
上の写真は、スローフードすぎなみTOKYOの佐々木さんがその場で書いてくださった
参加しての感想の言葉をしたためた書を持って微笑む佐々木さんと奥田シェフを中央に、
周りは各会の代表でお話いただいた方々です。
食談会はビュッフェ方式で行われました。
イルケが貸切りになるときにはいつもこのスタイルです。
『どんな形にしたらよりお客様に喜んでいただけるようにできるか、まだまだ模索中なのです。』
と、奥さんは話していらっしゃました。
ここで、頂いたメニューの一部を紹介しましょう。
・遊佐のマスのマリネ
・酒田沖のヒラメのバルサミコソース
・甘鯛とズイキの茎のペペロナータ
・庄内牛のカルパッチョ
・スーパー小松菜のアンチョビサラダ
・赤ネギとハタハタのアルケ風
・庄内牛の辛くてしょっぱい赤ネギ
・宝谷カブのピッツア
・ズイキのゴルゴンゾーラグラタン
まだ書いてもいいですか?(^_^;)
もう、この辺でやめときましょうか。。。。
この他にも、
「庄内豚」「庄内柿」「赤根ほうれんそう」「天然きのこ」「庄内麩」などなど
庄内をはじめとする山形県内の食材をふんだんに使ったお料理を運んでいただきました。
おいしい食事と楽しい会話が進むなかで、
店内に設置されたプロジェクターでは庄内の風景などが映し出されます。
すると、奥田シェフはマイクを握り、
今度は庄内の秘密について語り始めました。
庄内の海、川、山、丘、高原、畑、土、水、風、雪、砂丘などなど。。。
庄内がこれほどまでも食の宝庫である理由をみんなに説明していただきました。
そのあと、江頭先生による「在来作物」に関する講話も出て、
会場はまるで大学の講義が始まったかのよう。
本当に贅沢な時間を過ごすことができました。
畑を見学し、生産者の映像や庄内の映像を観て、おいしいものを食べる。
この一連の流れが、奥田シェフの求めていた形。
初めて鶴岡を訪れてくださったみなさんは、
いったいどんな感想を持って帰られたのでしょう。
今回、みなさんをお招きして黒子となりいろいろと動き回りましたが、
行き届かないところが多々あったかと思います。
それは、今後の課題としこれからもいろんなことを企画していけたらいいと思いました。
みなさんが『是非、また来てみたいなぁ〜。』なんて、
思っていただけたらこの会は大成功だったと思います。
そして、またたくさんの方々と出会えたことに心から感謝します。
『庄内には「四季」ではなく「十二季」ある。』と奥田シェフは言います。
山菜屋を生業としている私どもも『山菜の「旬」は10日』と言っています。
10日ごとにいろんな山菜の顔ぶれが変わっていく庄内の風土の中で、
まだまだ、勉強しなければいけないこともたくさんあるけれど、
この旬の時期に皆様のもとへおいしい天然の山菜をお送りするべく、
これからも頑張っていきたいと思っています。
最後になりましたが、
今回ご参加くださいました『スローフードすぎなみTOKYO』のサイトの中でも
庄内在来作物探検&食談会についてレポートいただいております。
見学したところの情報など、
ここよりも詳しくレポートされてますのでご覧下さい。