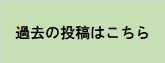昨日朝、米沢市内通勤途中で虹でてました、久しぶりで観たので、写真に収める・・そういえば虹に関わる曲は多い、『にじ』ケロポンズ 1990年は今年の秋の発表に向けて練習してる曲で、菅田将暉の虹は良く新月ライブで歌う曲です・・他に『虹を越えて』スピッツ 1996年・・『虹』L’Arc~en~Ciel 1997年・・『虹』福山雅治 2003年・・『虹』森山直太朗 2006年・・『虹』ゆず 2009年・・『にじいろ』絢香 2014年・・『虹』菅田将暉 2020年などなど他にもまだあるようだ・・ 虹は、平和や絆、希望等、ポジティブな事柄をを連想させるワードとして、さまざまな楽曲のタイトルや歌詞に使われているのですね。
HOME > 記事一覧
せみの抜け殻
昨日仕事終わって家の北側草むしり、するとウドに久しぶりセミの抜け殻ありました、小学生の頃は虫好きで、夕方家の周りの木に登ってくる蝉を捕まえて、家の中の植木を入れて早朝羽化したセミをよく見てましたね・・羽化した後はまた植木を外に戻してと・・よくそんなことをしてました・・今年は例年よりセミ少ないようです・・寝苦しいところにさらにセミの声が夏を増長させてましたが・・好きでしたね・・特にうるさいのがクマゼミということですが、東北では見れませんね・・熊セミは名の通り体長が約50mmで、日本で一番大きなセミと言われています。クマゼミは「シャッシャッ」という鳴き声である。この辺でも様々な種類のセミが生息し、夏の初めにニイニイゼミにはじまりアブラゼミ、ミンミンゼミ、ヒグラシ、ツクツクボウシなどとなる・・
キャンベルアーリー
我が家の黒ブドウ’Campbell Early)が色づいてきた、昔はこの黒ブドウとデラウエアだけだったったような気がします・・このブドウは1892年にアメリカで誕生したそうで、親の掛け合わせは「ムーアアーリー」×「ベルビデレ×マスカット・ハンブルグ」。日本に伝わったのは1897年(明治30年)頃とある・・昔は人気が高く、1970年代は生産量も多かったが、新しい品種が増えたことでキャンベル・アーリーの生産量は徐々に減少しているようです・・キャンベル・アーリーという名前は、アメリカの育成者ジョージ・W・キャンベル氏に由来するといわれています。ついこないだまで雨が降らずに色づいたのがしなびてだめになってましたが、この雨で生き返ったようです・・我が家の家庭菜園ブドウは黒ブドウとデラウエアです・・