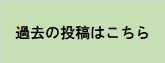昨日、朝の天元台高原です、すっかり秋の空になりました・・「天高く馬肥ゆる秋」がぴったしですね、「天高く」とは、空が澄み渡って高く見えるという意味ですよね。秋は空気が乾いているため空が澄んで見通しがよく、青色がくっきりとして、秋らしいイメージのあるすじ雲やひつじ雲など高い位置にできる・・いわし雲やうろこ雲・・さば雲などいろいろ
枝豆
我が家の家庭菜園、えだまめ収穫しました・・少し早かったようです・・実が小さかった、まだ残しても少し後に再度収穫です・・枝豆は未成熟の大豆を食用とする野菜で、枝付きのまま茹でて食用にしたことからこの名がついたとあります。穀物用としての大豆は、東アジア原産で、中国では紀元前2000年から栽培されている古い作物です。日本への渡来は明らかではなく、「古事記」や「日本書紀」に名前が見られることからも、かなり古くから伝わっていたことがわかります、日本でのえだまめとしての利用は、17世紀末の江戸時代から。当時は枝に付いたままの状態で茹でたものが売られており、その状態で食べ歩くファストフードのような存在でした。枝付いたままとは、意外でしたね・・根強い需要のある山形の「だだちゃ豆」、福島県・秋田県の「五葉豆」、新潟県の「茶豆」など、さや、豆が茶色味を帯びた茶豆系の品種や、丹波地方の黒豆など、地方には味の良い独自の品種がいろいろあります。
コスモス
我が家のコスモスが咲いてます、ピンクのコスモスが一般的ですね・・花言葉は「乙女の純潔」だそうで・・ピンクの色合いにピッタリな花言葉です。
淡いピンク色のコスモスと、濃いピンク色のコスモスが出回っていますが・コスモスの花は、ピンクや白に加えて濃赤、黄やオレンジ色、複色が登場し、年々カラフルになっています。性質はいたって丈夫で、日当たりと風通しがよい場所であれば、あまり土質を選ばずに育ちます。
日本の秋の風物詩となっているコスモスですがコスモスを「秋桜」と読むようになったのは、1977年にリリースされた山口百恵さんの楽曲「秋桜(コスモス)」が大ヒットしたことがきっかけなんですよね、この曲の作詞・作曲はさだまさしさん、歌詞の中で「秋桜」と表記しつつ「コスモス」と読ませたことで、この読み方が一般に広まりました。本来、「秋桜」は「あきざくら」と読み、秋に咲く桜に似た花という意味で名付けられた漢字表記・・古くからあったわけではなく、コスモス自体はメキシコ原産で、明治時代に日本に伝わった外来種なんですね・・