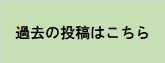昨日早朝の天元台高原、雲海から種蒔山とその奥に飯豊山が久しぶり見えました・・写真手前の水は天元台の水源からの長命水・・この4連休はあいにくの天気、連休明けの昨日14日も朝だけ飯豊も見えましたが・・その後はガス視界、雨も降りだして、気温も下がる・・そんでも山頂目指して登山客が行く・・昨日98座というかた(女性)がいました、しかし西吾妻は3回目だそうで・・残り2か所ですが仲間8名と西吾妻に来たそうです・・来週99座目に行くそうだ・・天気は多少悪くても何のそのだそうで?・・とても元気な女性でした・・以前99座目というかた(女性)もいた・・こうしてみると男性より女性が多い登山客・・女性強しですね・・
HOME > 記事一覧
冬に向けて
我が家の家庭菜園で採れた枝豆、友人にお裾分けしても余った枝豆は茹でて冷凍に、サツマイモも調理するサイズにして冷凍庫に・・冬に向けて保存します、昔は冷蔵庫もなく、干したり、漬物したり、土に野菜埋めたり冬の備え大変でしたね・・そんな光景は昭和の30年代まで・・冷蔵庫、スーパーの誕生でいつでもなんでも手に入る時代に・・斉藤和義のデビュー曲・・”欲しいものならそろいすぎてる時代さ・・僕は食うことに困ったことなどない・・緊張感を感じられない時代さ”という歌詞がある、そうだねと思うが、何と幸せなことか・・世界では食うことどころか、紛争の中で明日の命がわからんとこで生きてる人がいる・・考えさせられる
サンマ
昨日は、我が家で行う月二回のギター練習日、15時頃から夕食準備開始して、16時頃に集まり、夕飯出来次第の夕食となる、昨日は秋といえば”サンマ”というリクエストに応えて、私も今季初のサンマ、大根おろし添えで・・昔サンマは100円とか安い時期がありましたが、昨日買ったのは2匹で税込み640円と高くなりましたね・・でも秋にサンマは食べたくなりますね、昨日は我が家の菜園で採れたサツマイモ、ピーマン、シシトウ、カボチャのてんぷら、サラダにはミニトマトともう最後のキュウリを添えて、枝豆も我が家の菜園もの・・今年初の我が菜園の疎抜き大根で炒めもの・・なんともうまかった・・そして新米”雪若丸”で五目御飯・・雪若丸はモチモチした触感で五目御飯にはよく合うね・・