都会を離れて10年たちました、毎年絵画サークルの展示で町田にはいく、それと冬に軽井沢プリンスホテルスキー場のイントラバイトの帰りか行きがけに東京の孫を見に行くので年二回ほど都会の空気を吸うことになる・・でも改めて都心に行くでもないので東京満喫することは少ない、思えば都会に出た最初の一年は同期や友達と頻繁に都会散策したものだ・・青山通り、新宿、渋谷、池袋、下北沢や自由が丘、横浜とどこも人でいっぱい・・刺激もいっぱいでしたが、やがてみんな普通に戻る・・特に用事がなければ行くことはなくなる・・がしかし、都会から離れて思うことは、専門街という大きなところがる、道具街、楽器街、築地市場、古本街などなど田舎では考えられない品揃い、今はネットで検索してどこいても手に入るのだが、やはり専門街でみるのは楽しいのだ、今回はギター探しに東京へ弟の帰省した帰りの車に便乗して楽器街巡りした・・なんといっても御茶ノ水の楽器街は外せない、江戸時代は、神田川北岸の湯島の西辺を指した『おちゃの水』。この地にあった高林寺の井戸水が良質で将軍家に献上されたことが地名の由来とされる。神田川(外堀)沿いに大樹が鬱蒼と茂り、茗渓(めいけい)とも呼ばれる景勝地でもあったという・・神田上水を渡す懸樋が万治年間(1658-1661)に架けられてから、江戸名所の一つとなった。この懸樋にちなみ、懸樋の西に架かる橋を水道橋と呼ぶようになる・・そして明治大学、日本大学、東京医科歯科大学、順天堂大学など、数多くの大学や専門学校が集まる日本最大級の学生街となる。このため、街全体が若いエネルギーと活気に満ち溢れています。活気や雰囲気は、時代とともに変化を遂げてきた。学問と文化の中心地:江戸時代から学問の中心地であり、昌平坂学問所(湯島聖堂)が設立されて以来、多くの学問を志す人々が集まりました。時は流れ1970年代から80年代初頭にかけては、「日本のカルチエ・ラタン」と呼ばれ、学生運動の熱気やそれに続くサブカルチャーが生まれた街でもありました。特に、専門学校に通う学生が増え、ファッションやデザイン、音楽といった分野の学生が街を歩くことで、街全体がおしゃれに洗練されてきた・・そんなお茶の水駅降りてすぐに楽器店街となる・・1975年初めて来たときに驚いたものだ・・なぜか若かった頃のワクワク感がよみがえる・・御茶の水から渋谷、新宿と足を延ばして楽器店巡りした・目当てはネットでも検索していたエピフォン・カジノ・ナチュラル・・ネットで相場観をみてるので結局買わないであちこち歩くことになる・・一巡して1~3万ほどばらつくことがわかる・・あまりありすぎても迷ってしまう・・結局2日間はみて歩き、買わずにネットで購入でいいかとなるが・・一番値下げが大きかったお茶の水に寄る、東京駅はすぐ近い・電車時間気にしながら、結局買うてしもうた・・まだ物が増える・・困ったものだが買った瞬間は幸せホルモンが出ますね・




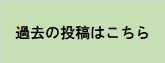
この記事へのコメントはこちら