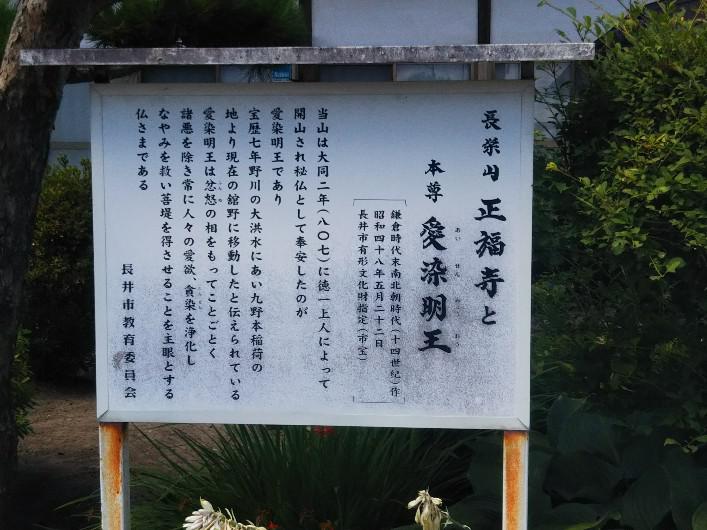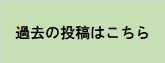先月11月5,6日と西会津方面に旅行、史跡慧日寺跡(しせきえにちじあと)よりました、広大な寺跡は昭和45年に国の史跡に指定され、復元整備が進められているということです。平成20年に金堂と中門が復元。さらに金堂内の展示物として薬師如来坐像が復元制作され、平成30年夏から一般公開されています。敷地内には、慧日寺を開いた徳一菩薩の墓と伝えられる平安時代の石塔「徳一廟」があります。かつては三重と思われていましたが、発掘調査により五重の石塔であることが分かっている、史跡慧日寺跡には、ほかにも仁王門や薬師堂など多くの見どころがあります。
樹齢800年を数えるエドヒガンザクラ「木ざし桜」もあり春は桜が楽しめますね、平安末期ごろ、慧日寺の宗徒頭・乗丹坊が挿した桜の杖がこの木になったという伝承が残っています。種まき桜ともいわれて花が咲き始めると田畑作業を始める目安とされていました。とある、マップみてゆっくり散策そこそこの運動になり、見ごたえもありました。