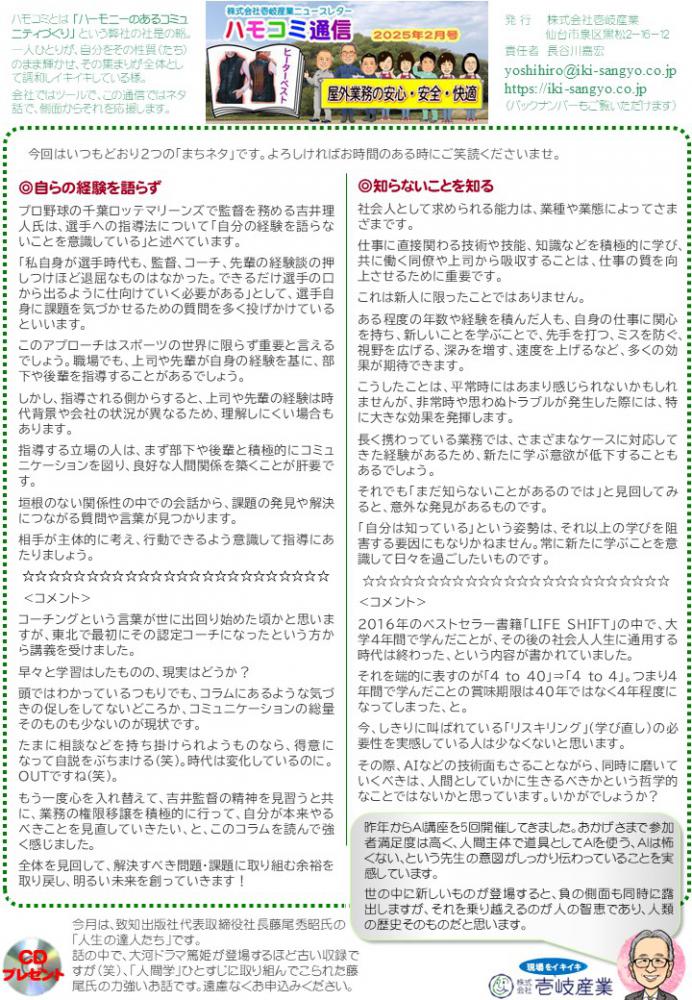生活に取り入れたり、仕事で生かすなどしていただけると本望です。
◎自らの経験を語らず
プロ野球の千葉ロッテマリーンズで監督を務める吉井理人氏は、選手への指導法について「自分の経験を語らないことを意識している」と述べています。
「私自身が選手時代も、監督、コーチ、先輩の経験談の押しつけほど退屈なものはなかった。できるだけ選手の口から出るように仕向けていく必要がある」として、選手自身に課題を気づかせるための質問を多く投げかけているといいます。
このアプローチはスポーツの世界に限らず重要と言えるでしょう。職場でも、上司や先輩が自身の経験を基に、部下や後輩を指導することがあるでしょう。
しかし、指導される側からすると、上司や先輩の経験は時代背景や会社の状況が異なるため、理解しにくい場合もあります。
指導する立場の人は、まず部下や後輩と積極的にコミュニケーションを図り、良好な人間関係を築くことが肝要です。
垣根のない関係性の中での会話から、課題の発見や解決につながる質問や言葉が見つかります。
相手が主体的に考え、行動できるよう意識して指導にあたりましょう。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
<コメント>
コーチングという言葉が世に出回り始めた頃かと思いますが、東北で最初にその認定コーチになったという方から講義を受けました。
早々と学習はしたものの、現実はどうか?
頭ではわかっているつもりでも、コラムにあるような気づきの促しをしてないどころか、コミュニケーションの総量そのものも少ないのが現状です。
たまに相談などを持ち掛けられようものなら、得意になって自説をぶちまける(笑)。時代は変化しているのに。OUTですね(笑)。
もう一度心を入れ替えて、吉井監督の精神を見習うと共に、業務の権限移譲を積極的に行って、自分が本来やるべきことを見直していきたい、と、このコラムを読んで強く感じました。
全体を見回して、解決すべき問題・課題に取り組む余裕を取り戻し、明るい未来を創っていきます!
◎知らないことを知る
社会人として求められる能力は、業種や業態によってさまざまです。
仕事に直接関わる技術や技能、知識などを積極的に学び、共に働く同僚や上司から吸収することは、仕事の質を向上させるために重要です。
これは新人に限ったことではありません。
ある程度の年数や経験を積んだ人も、自身の仕事に関心を持ち、新しいことを学ぶことで、先手を打つ、ミスを防ぐ、視野を広げる、深みを増す、速度を上げるなど、多くの効果が期待できます。
こうしたことは、平常時にはあまり感じられないかもしれませんが、非常時や思わぬトラブルが発生した際には、特に大きな効果を発揮します。
長く携わっている業務では、さまざまなケースに対応してきた経験があるため、新たに学ぶ意欲が低下することもあるでしょう。
それでも「まだ知らないことがあるのでは」と見回してみると、意外な発見があるものです。
「自分は知っている」という姿勢は、それ以上の学びを阻害する要因にもなりかねません。常に新たに学ぶことを意識して日々を過ごしたいものです。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
<コメント>
2016年のベストセラー書籍「LIFE SHIFT」の中で、大学4年間で学んだことが、その後の社会人人生に通用する時代は終わった、という内容が書かれていました。
それを端的に表すのが「4 to 40」⇒「4 to 4」。つまり4年間で学んだことの賞味期限は40年ではなく4年程度になってしまった、と。
今、しきりに叫ばれている「リスキリング」(学び直し)の必要性を実感している人は少なくないと思います。
その際、AIなどの技術面もさることながら、同時に磨いていくべきは、人間としていかに生きるべきかという哲学的なことではないかと思っています。いかがでしょうか?