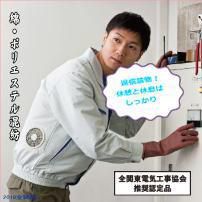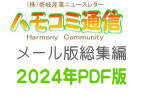生活に取り入れたり、仕事で生かすなどしていただけると本望です。
◎自分との約束はなぜ破られる?(『決まりごとの心理学』より一部抜粋)
立正大学経営学部教授 山本仁志
それを守れないのは、あなたの心が弱いからだけではありません。そこには頭の中でのある種の打算というか計算が働いているのです。
例えば「ダイエットのために毎日、ランニングをする」という決意はなぜ守られにくいのでしょうか。
今ここに1万円と1万5千円があるとします。 どちらを選びますか? 多くの人は後者を選ぶはずです。
では今すぐ1万円の現金を受け取るのと、1年後に1万5千円を受け取るのとではどうでしょう。
「今の1万円」を選択する人もそれなりに出てくるのではないでしょうか。 そうです、 将来の価値は低く見積もられがちなのです。
この性質を時間割引と言います。これが自分で決めたことを守れない一つの要因になっています。
ランニングは今すぐ行なわなければならない一方で、スマートな体型は将来にならないと受け取れません。
この時間の差が、 決まりごとを守りたい自分と守れない自分の間に横たわっているのです。
ここで大事なことは、 時間割引を敵視してもしょうがないということです。賢く付き合う必要があります。では、どのように時間割引と付き合えば良いでしょうか。
それは「ハンドルを投げ捨てろ、今日の飴を用意しろ」です。
「ハンドルを投げ捨てる」とは言わば、自分を逃げられない状況に置いてしまうことです。
例えば、 入会金を支払ってスポーツジムに通い、家族にもそのことを伝えるというようなことです。こうすると、週末に運動をしない選択をしにくくなるでしょう。
「今日の飴を用意する」とは、決まりごとにほんの少しの報酬を用意することです。
例えば私はランニングをすることでポイントが貯まるアプリをスマートフォンに入れています。 確かに貯まるポイントは微々たるものです。
しかしもともと運動しなくてはと思っているのですから、後押しする力はこれで十分なのです。
え、ハンドルを捨てる決心ができないし、今日の飴も用意するのが面倒くさいですって? その場合、あなたはそもそもその課題に取り組みたくないと心の奥では思っているのです。
◎オールラウンドな生き方
昨年7月に発行された新紙幣の五千円札の肖像となっている津田梅子は、明治から大正にかけて女性の地位向上と女子教育に尽力した教育家です。
明治4年に日本初の女子留学生の一人として6歳で渡米し、 17歳で帰国後、華族女学校などで英語教師を務めました。
25歳から2年半の再留学を経て、明治33年に女子英学塾 (現・津田塾大学)を設立しました。
開校式では「All-round womenとなるよう心掛けねばなりません」と述べたと記録されています。
これは「英語だけに囚われず視野の広い女性を目指す」ことを薦めたものであり、現在も建学の精神として受け継がれています。
彼女が目指した女子教育の目的は、男性と同様の社会的地位を得ることではなく、様々な分野を広く学び、必要とされる人間になることでした。
私たちの職場においても、専門分野に磨きをかけることはもちろん、専門外の分野にも目を向けて広く見識を深めることが重要です。
様々な場面に対応できるオールラウンドな生き方を目指したいものです。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
<コメント>
明治4年といえば、まだ江戸の名残がある時代。そんな時代に6歳の娘をアメリカに留学させる親ってどんな人?
父親は津田仙。江戸末期1867年に通訳として渡米し、男女平等の世界を目の当たりにしたことで、日本初の女子留学生のアメリカ派遣事業に、梅子を応募させた、と。
女子は13歳で元服という時代ですから、当時の6歳は、今の6歳よりはるかにしっかりしていたのでしょう。
専門分野に磨きをかけつつも、幅広く深い見識を得ようと努め、社会の必要を感じて動く、という考え方は、私が目指しているものと近いので選ばせていただきました。