▼呼びかけ人メッセージ
|
武力による国際貢献は、イラク問題で解決のむずかしいことがわかる。にもかかわらず、憲法九条の改悪がすすんでいるようです。
私は、自力で幼児の保育にあたっていますが、今0才の幼児が5名通園しています。 (1才〜2才15名、3才〜5才20名) 先ず、0才の児は私になれてもらう方法で保育をはじめます。すると他の保育士に抱かれても泣きやまない子を、私が声をかけ抱いてやるとピタリと泣き止むのです。このかわいい子らが国際紛争などにまき込まれない平和な生活が期待できる基本的なものが、憲法九条だと思います。ですから、九条を守る運動に大賛成なのです。 安食 正一(牧師) |
|
今年、“天命を知る”という50代となりました。今まで唯自分の楽しみだけで生きてきました。そろそろ周辺の方々にお役に立てることをと、先日『ヒロシマ・ナガサキ原爆写真展』と映画『父と暮せば』の上映会に関わりました。
二つのことを通して私の心で繰り返されたのは《記憶》という言葉でした。 私には直接的な戦争体験はありませんが、原爆の写真をパネルに張りながら、死んだじぃちゃんのことを思い出していました。体が弱かったので出征できず後ろめたさに傷ついていることを感じた子供なりの私自身の《記憶》が蘇りました。 映画の中では父が、生き残ってやはり後ろめたい娘を諭し励ましました。「あよなむごい別れがまこと何万もあったちゅうことを覚えてもろうために生かされとるんじゃ。おまいの勤めとる図書館もそよなことを伝えるところじゃないんか」と。《記憶》を伝えるために生かされているのだと娘は再生するのです。 一人ひとりの《記憶》がしっかりつながって、それは“国の記憶”となりました。それが日本国憲法の前文であり第9条の非武装平和主義ではなかったのでしょうか。 木村久夫(さくらんぼ共生園園長) |
|
私にとって憲法とは、真の男女平等実現。子どものころ、出羽三山へのお参りに兄だけがいけて女であるためにゆけなかったひどくショックを受けた思い出があります。
日本国憲法は、すべて変えることなく憲法の実現のための政治をして欲しい。九条はもちろん一三条、十四条、二十条、二十四条、二十五条など、私たちが生きてゆく基本となるものだから、現憲法の遵守のひとことにつきると思う。 加藤美枝子(寒河江生協理事会議長) |
|
村山市岩野に万歳石というものがある。万歳石は、村上定治郎さんが、1935(昭和10)年頃、水田から発掘した、長さ1・5m、幅1・4m、高さ0・5mほとの自然石で、上面は平坦な半円形である。正面の「万歳石」は、内閣総理大臣佐藤栄作書。側面の銅板には「われわれは体験した 戦争は不幸を生み平和は繋栄をもたらすことを…出征者はこの石の上に立って送ってきたむら人のばんざいの声に応え最後の挨拶をすることを例とした」とある。
軍国の教育を受けた若者のなかには「蒋介石の首を取ってくる」と言った人もいたという。解説文には「太平洋戦争には123名の出征者があったが、戦没者は24名に達した」と記されている。定治郎さんの長男もシベリアに抑留され、戦病死した。万歳石は戦争の悲しみと怒りの象徴で在る。憲法9条が危ない今、岩野の路傍の石の重みを再認識したい。 宇野修平(西根・郷土史家) |
|
昨日、山形に研修に来ているベトナムの青年たちと会いました。
平和で豊かな国を自分たちが作っていくという気持ちがあふれているように見えました。 暴力からは憎しみ・悲しみ以外何も生み出すものはありません。 私たちの誇る”9条”を守るため、今していることを彼らに話すつもりです。 今週末、青年は我が家にホームスティにやって来ます。 2005.8.2 田中ふみ子(白岩・羽陽学園短期大学教授) |
|
戦後60年の間、日本が仕掛けた戦争で、人を殺したり、殺されたりしたことが、1度もありませんでした。これは「平和憲法」を持つ国民の大きな誇りです。
今、戦場であるイラクに自衛隊が派遣されています。九条改悪の企みが大きく進 行しています。 日本が戦争のできる国になったら大変です。どんなことがあっても、 九条だけは守り抜きたい。そのために微力を尽くそう、と思います。 尾形 敏(緑町・元校長) |
|
私たち一家は昭和十六年八月に郡山の在から天童の小さな寺に越して来ました。
父は、明治三十三年生まれ。典型的な明治型正義派でした。その年の十二月に第2次大戦が始まり小さな寺での初めての生活は、とても大変でした。舞鶴山の草を生きる糧にしました。 新聞の切抜きが趣味だった父は、皇室関係、戦争関係の記事を毎日のように切り取っては、戦果の報に一喜一憂していました。戦争が終わったときの父は狂人のようでした。「国に、軍に、そして新聞にまでだまされた」と怒りに震えていました。それまで大切に切りためていた記事を残らず庭に持ち出し泣きながら燃してしまいました。 ラジオ番組「真相はこうだ」が始まると、「いまさら何を言うかー、」とバチッと切ってしまいます。その父も二十六年に亡くなり、新憲法についての意見を話し合う間もありませんでしたが、もしあの一途な父がいきていたら「また国はうそをつくのか」と激怒したかも知れません。一度決めたことを、いつの間にか、そして何となくすり替えしまうようなやり方は許せません。父の怒った顔を思い浮べながら、平和な国日本の基本は守らねばと強く思っています。 土田ヨウ子 (下河原・元教員) |
|
「仕事柄」というわけでもない。「生まれつきの性分」というばかりでもない。他人に生き方を指示されることは大嫌いなのに、他人様に「こうしたほうが良いかも知れないよ」と助言を与える立場になってしまっている今の自分。
職業は・・・、音楽家、短大の教員、演出家、歌手・・・。要するに舞台やら、人前で何かを表現することにかかわっているわけです。 この日本の持つ“戦争はしないぞ!!”というポリシーをよその国の人たちにも紹介したい(決して押しつけはしないけれど、米国の独善主義のようには・・・)とは思うのだが、いかんせん、日本の国の中にも、“戦ってこそ、軍備をもってこその自立した国家”と叫ぶ人たちが多すぎて、“あんたの国はどうなっとるんじゃい!?”と紹介した外国人に逆に突っ込まれそうなのが嫌ですね。 せめて“日本は戦わないよ”という9条の志を理解し、共感する人を増やすための場―に、このネットワークが活用されることを願います。 高橋 寛(島、声楽家・演出家・羽陽学園短期大学講師) |
|
現在の国際情勢は、不幸にもテロが横行する社会になっています。
テロの要因となるものには宗教、貧困、飢餓、富のアンバランスなどがあるといわれていますが、根本には、平和希求精神の欠如にあるのではないかと考えます。 幸いにも日本国家には「武力による紛争解決手段」をとらない国家を貫いております。 私は、このような国家に生まれたことに誇りを持っています。 松田伸一(六供町、環境カウンセラー) |
|
私の家族は、戦争の話題、政治問題などを茶の間の話題にする人ではありませんでした。子供時代、学校で教わったそれらのことは、あまりにも感情のない事実の羅列で、戦争については、被害者としての面のみをクローズアップして知らされたように思います。大人になって、加害者になる苦しみや、集団の狂気、暴力の連鎖・・・、飢餓や、環境問題まで少し違った角度からも見ることができました。
子供にかぎらず、大人も、日常の生活が平和であれば、興味を持って自分から情報を仕入れようとしない限り、戦争について理解を深めていくことはないと思います。いつの間にか、気がついたら戦争に巻き込まれていた・・・、ということが本当になりそうな不安なこのごろの情勢です。今こそ、第9条の問題にしろ、もっと身近に話題があるべきだと感じています。 高橋 まり子(島、声楽家) |
|
息子や夫や孫たちが戦争にかり出されないために 集まろう 話し合おう 戦争で亡くなった父や兄たちのことを思い出すために 集まろう 話し合おう 「戦争のできる国」か「戦争のできない国」か 集まろう 話し合おう 私たちの憲法は本当に時代遅れなのだろうか 集まろう 話し合おう 平和のために私たちが何をしなければならないか 集まろう 話し合おう 不戦を誓い合ったあの頃を思い出すために 集まろう 話し合おう 集まることが話し合うことがどんなに大事か考えるために 集まろう 話し合おう 私たちは私たちの未来に責任があるのだから 集まろう 行動しよう 粕谷俊矩(西根、山岳愛好家) |
|
私たちにとって「九条」がどんなに大事なものか。これは身近に戦争の怖さを知らないとわからないのでないのかな。あるいは充分に知っていたとしても六〇年も過ぎてしまった今は、すっかり忘れてしまって、今の平和なくらしが「九条」に守られているから・・・などということも気付かずにいるのでしょうね。私の場合は十五歳で旧制女学校の2年生で敗戦となりましたが、田舎に生まれたおかげで、家を焼かれることもなく、父が病弱だったので出征することもなく、一家揃って何とか生きることができました。
しかし、人生の伴侶として出会った人は、土浦海軍航空隊の特攻要員として敗戦を迎え、結核のため片肺で生きなければならない人でした。甲種合格で航空隊に入った青年が1年後には身体障害者となり一生片肺で生きならければならかったのは戦争のためでした。九条の大切さは、身をもって感じているものです。 長岡禮子 (六供町・元教員) |
copyright/aone
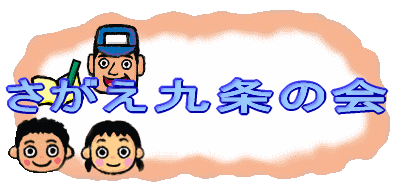





昭和26年4月、私は山形師範最後の卒業として、当時の北村山郡戸沢中に赴任した。中学校は山の中腹にあり、小学校は道路そばにグランドがあり、両校は長い階段で往き来ができるようになっていた。
神町に駐屯していた進駐軍は、高射砲を牽引した車、幌をかけた車、兵隊を満載したトラックで毎日のように大高根演習場を往復していた。休み時間に校庭で遊んでいた子供たちは、車の音を聞くと一斉に道路側にかけより柵に寄りかかり「サンキュウ」「サンキュウ」と叫んでは両手を伸ばす。兵隊たちは笑いながら飲みかけのジュースの缶、ガム、チョコレートのかけらなどを投げる。職員室の窓越しにそんな子供たちの姿を見ていた教師たちの思いはどんなだったであろうか。止めることもできなかった。
6月、今日から田植え休みに入るという日、「矢の下の子供が死んだらしい。中学生も被害にあった」と知らせが入った。
進駐軍は毎日のように実弾演習をしていた。そのため決められた曜日以外は、山にある畑にも行けなかった。その日の昼休み時間に子供たちは生活費の一部になる鉄くず拾いに山にいったのだ。4年生の男の子は不発の手榴弾を見つけ両手で掘って爆死。傍に立って見ていた中2の女子は大腿部や腹部に破片を受けてショック死。男の子の姉で中1の私の担任だった子は、足指などの怪我で東根日赤病院に運ばれたが軽傷だった。男の子は、みかん箱に藁を敷いた中に入れられ、粗末な家の薄暗い奥のむしろの上に置かれていた。手首の片方は見つからなかったという。猟師をしていた父親は、山に入れないため収入もなく、囲炉裏のふちにあぐらをかいてぼんやりキセルで煙を吐き、病弱な母親は、部屋の隅の薄い布団の上でただうずくまっていた。
1学期末、通知表を持っての家庭訪問。道路の東側からドーンという高射砲の発射音。ヒュルヒュルと頭上を過ぎる鋭い音、間もなくダダーンと西側の斜面にとどろく爆発音。戦争は終わったのだと心に言い聞かせつつ、足が絡むような思いだった。あの下で暮らしていた人たち。「スイカ、駄目になったべはー」「とっきび、烏にくわったべはー」とため息をついていた人たち。あの惨めな思い。
戦争はいや。負けるのはいや。でも勝つのもいや。もし勝っていたらと思うと別の意味でゾッとする。人殺しはいや。
負けたことによって生まれ変わり、たとえ外国の力を借りたとしても新しい憲法ができたことで60年以上も戦争しなかった国。平和を地でいけた国、九条を守ることはこれからもまたずっと平和を続けるということ。他の国の戦争にも手を貸さない。私たちの子孫の手を血で汚させない。文字だけの言葉だけの平和であってあっはいけない。それが私たちの心からの願い。
60年以上たってもまだ属国のようにアメリカのいいなりにならないのは何故。いつまで続くのか。独立国としての自負を持たねば。愛国心というのは戦争をすることではない。真に自国を愛する。自然に愛する。日本に軍は不用。実質ともに平和な国日本として世界に誇れる国でありますように。
九条は変えない! 変えさせない!